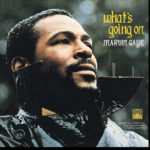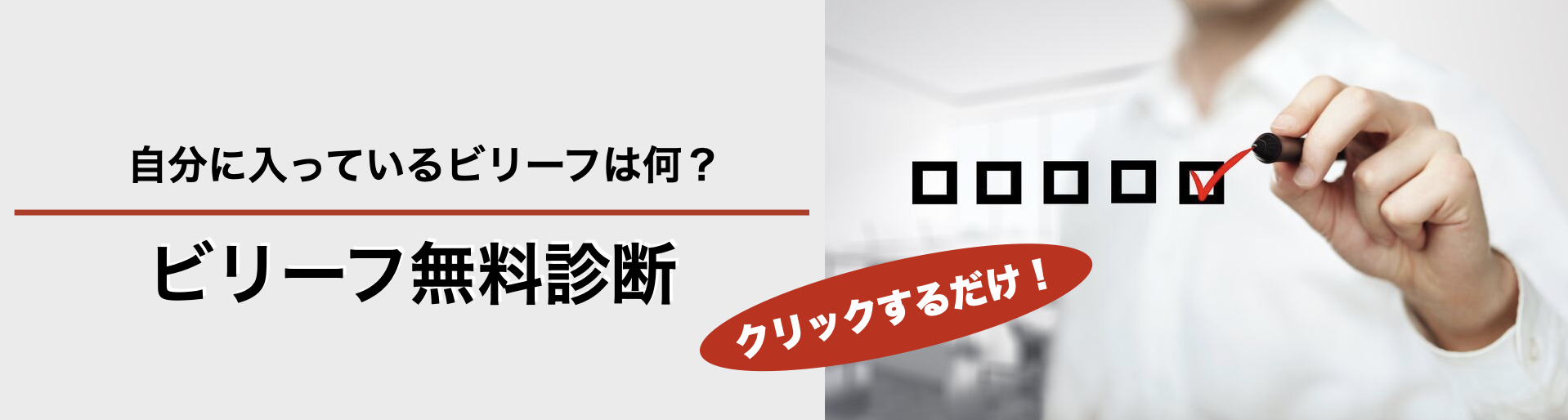私たちは、なぜ音楽を聴き、音楽を必要とするのだろう?
それは
自分の感情を感じるため
ではないかと私は推察しています。
感情を抑えている人ほど、音楽を必要とする・・・・のかもしれません。
感情を抑え過ぎる私たち
私たちは大人になるに従って、自分の感情を抑えるようになってきます。
赤ちゃんみたいに、いちいち泣いたりわめいたり、はしゃいだりして感情表現していたら、
社会生活に差し支えもでてきますからね。
「感情をコントロールできる」というのが大人の条件であり、
「できる人」の重要なスキルと見なされていたりするわけです。
それはそれでオッケー。
それも必要なことです。
しかし一方で
それをやり過ぎているうちに私たちは
「抑える」だけにとどまらず
「そもそも感じないように」してしまうことがあります。
無意識のうちに、ですけどね。
あまりにもガマンしすぎて、
自分の感情が何なのかわからなくなっていることもよくあります。
感じないようにすることのメリットは、
とりあえず傷つかないことや、人とぶつからないこと。
そして、ただ目先の
「やらなければならないこと」
「そうすべきこと」
「そう決まっていること」
「そう言われたこと」
に従って、淡々と行動できることです。
ある意味、サイボーグ化した仕事人間にだってなれるってこと。

そうやって表面的には、それでうまく社会生活をこなしていくことができますが、
しかし私たちは人間なので、やっぱり感情のエネルギーが必要なんですね。
感じないようにしていたって、心の深層には、本当は感じていた感情というのが、仮死状態にさせられています。
そこで音楽
そこで、音楽なのです。
音楽は、思考を通さずダイレクトに感情にアクセスする力があります。
私たちは、音楽というものを借りて、実は自分の感情にアクセスしているのかもしれません。
私たちは、何かの感情を感じたくて、あるいは何かの感情を解消したくて、音楽を聴く。
感情のエネルギーを取り戻すために、音楽を聴く。
なぜなら、上記のように私たちは、日常生活で感情を抑える、感じないようにするということをかなりやっているからです。
音楽を聴いてなんらかの感情を動かす、ということ。
それは、音楽に心を動かしているようでいて、その奥にはすでに自分が本当は感じたい感情があって、
でもそれはなかなか直接的には感じられないために音楽を通してそれを感じさせてもらっている・・・
ということなのではないかと、私は考えています。

感情を音楽に投影する
心理学では「投影」という言葉があります。
一言でいうと、自分以外の何かに、自分の感情を映し出して感じることです。
無意識に自分が感じないようにしているものを、自分以外の何かの上に見て、そこから間接的に感じるのが、投影という心のシステムです。
まさに音楽とは
まことに豊かで多彩な「投影の器・スクリーン」だな、と
私は感じます。

たとえば、切ない歌が心にしみるのは、自分の中に切ない感情があるからです。
音楽に触れて「切ないなー」と感じることで、
自分の中の切ない感情にアクセスし、味わって無意識に解放・浄化しているということです。
ネガティブ・ポジティブ含めてあらゆる感情を、私たちは音楽に投影して具体的に感じることができ、
結果としてあるカタルシス(解放・浄化)を得ることができるのです。
そういうことを、私たちは音楽を通してやっているのではないかと、私は考えます。
感情を抑えている人ほど、音楽を必要とする(仮説)

そういうわけで、私の仮説によれば、日ごろ感情を抑えている人ほど、切実に音楽を必要とします。
音楽というものが、なくてはならない唯一の友のようになる場合があります。
そうやって、人間の生きるエネルギーそのものである「感情」を音楽によって取り戻して、どうにかこの世を生きている人はおそらくたくさんいます。
ほかでもない、私自身がまさにそうやって生き延びてきた1人ですし、他の人の例を見ても、どうもそんな気がしています。
そして、今私が、あんまり以前ほど音楽を必要としなくなったのは、
自分の感情とのつき合い方が少しわかってきたからではないかと思うのです。
感情を自分の感情として感じたり、受け入れたりすることに慣れていくと、
わざわざ音楽に投影しなくても済むようになってくるのではないかと見ています。
あるいは、投影するような聴き方ではない、何か別の回路による聴き方へと変化していく可能性も考えられます。
これも仮説ですが。
つまり、今日の結論。
人は、なかなか感じにくい自分の感情を
音楽に投影して感じ、解放して
生きるエネルギーにする。
これが、私が考える「人が音楽を必要とする理由」の一つです。